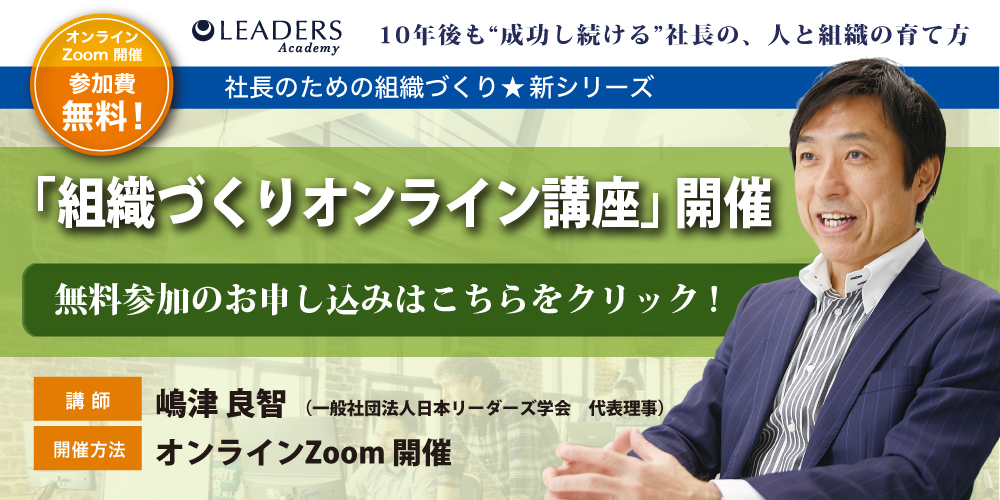本記事の著者/嶋津 良智
一般社団法人日本リーダーズ学会 代表理事
もっと’稼ぐ’組織を作る『上司学』『組織づくりの12分野』メソッドの開発者であり、リーダー育成の第一人者。
大学卒業後、IT系ベンチャー企業に入社。同期100名の中でトップセールスマンとして活躍、その功績が認められ24歳の若さで最年少営業部長に抜擢。就任3ヶ月で担当部門の成績が全国ナンバー1になる。その後28歳で独立・起業し代表取締役に就任。M&Aを経て2004年52憶の会社まで育て株式上場(IPO)を果たす。2005年次世代リーダーを育成することを目的とした教育機関『リーダーズアカデミー』を設立。2007年シンガポールへ拠点を移し、講演・企業研修・コンサルティングを行う傍ら、顧問・社外役員として経営に参画。業績向上のための独自プログラム『上司学』が好評を博し、世界15都市でビジネスセミナーを開催。延べ50,000人以上のリーダー育成に携わる。2013年 日本へ拠点を戻し、一般社団法人日本リーダーズ学会を設立。世界で活躍するための日本人的グローバルリーダーの育成に取り組む。
部下を育てるには何をすればよいのか?
リーダーの責任の1つが「育成責任」です。部下をどのように育てればよいのかと悩まれているリーダーからの声が私のところには日々届きます。
そんな部下を育てることに悩んでいる全国のリーダーのために 、合計17つに部下育成のポイントをご紹介いたします。
これらを意識しておくことが、部下を育てることのできるリーダーになる第一歩となります。
1.仕事の楽しさを部下に伝える
リーダーにとって、部下に信頼されることは大変に重要なことです。この部分がしっかりできるかできないかによって、リーダーとして成功するかしないかが決まります。
それには、まずリーダー自身が部下から見て魅力的な人間に思えることが重要です。魅力的な人間――それは、器が大きい、決断力がある、業績をあげている、面倒見がいい、といったことです。
それとともに、魅力的な人間であるためには、リーダー自身がイキイキと働き、仕事を楽しんでいなければなりません。いつも怒った顔ばかり見せたり、ため息ばかりついてつまらなそうに働いていたりするのでは、部下まで憂鬱な気分になってしまいます。
私自身、学校を卒業して新入社員になったとき、当時の上司から、「歯を磨いているときも、お風呂に入っているときも、トイレに行っているときも、酒を飲んでいるときも、頭から仕事が離れなくなったときは、良いポジションで仕事をしていられるよ」と言われました。そのときは、「そんな仕事漬けなんて、冗談じゃない」と思ったものです。しかし、2、3年後には、自分がみごとにそのような状況になっていたのです。これは、仕事の楽しさを覚えたからなのです。
経営者やリーダーといわれる人たちも、つねに頭から仕事のことが離れない状態にいるはずです。電車のなかでも「あ、今度の仕事にはあの発想を取り入れよう」、あるいはシャワーしながらも「明日は、あいつにこんな声をかけてやろう」、などと考えているのではないでしょうか。これは、仕事を楽しいと思えるからこそなのです。
全身で楽しみながら仕事をする。それは、傍から見て魅力的に輝いて見えます。
仕事を楽しんでやっている態度は、部下にもしっかり伝わります。やがて、部下もがんばって業績をあげれば大きな達成感が味わえ、それがとても楽しいことなのだということを体得していきます。
楽しみながらやる仕事なら、どんなときでもがんばれるし、多少の失敗ではくじけないものです。部下がイキイキと働く組織はとても強くなります。
2.部下のモチベーションを上げるには
時代に即応させて企業を変革し、活気ある職場にするには、働く社員一人ひとりのやる気 (モチべーション) を引き出していくことが大きなポイントとなります。
そのために、リーダーは、部下がイキイキと働けるような職場環境を整える役目を負っています。それとともに、部下自らが問題解決に積極的に取り組めるように、意識の向上をはかっていくことです。
これまで多くの会社では、部下に地位や報酬を与えて、モチべーションを高めてきました。たしかにそれも一つの方法です。
しかし、それだけでは部下はついてきません。とくに最近は価値観が多様化し、若い人のなかには、がんばるということをむしろ「ダサイ」と感じている人さえいます。ですから、従来の方法だけではやる気にならないのです。今の若い人たちは「楽しい」とか「盛り上がる」ということが大好きですから、仕事が楽しいということは重要な要素となります。
仕事を楽しんでやれるようになれば、必然的にモチべーションはあがります。
そこで、部下に仕事を任せ、権限委譲をするのです。そこでは部下は自分で考え、チャレンジし、自らの力でやっていかなければなりません。最初は危なっかしくても、任せれば部下は懸命に取り組みます。
苦労もあるけれど、責任のある仕事を成し遂げれば、大きな達成感を味わえます。この達成感こそが、仕事をするうえでの最大の喜びなのです。リーダーであれば、部下にこの気持ちをまず味わわせてあげることが必要です。
能力以上と思われた仕事でも、その人なりに成し遂げられれば、きちんと評価し、賞賛してあげます。するとそれが自信になり、部下は大きく成長します。
またしばらくしたら、さらに一段上の仕事にチャレンジさせてみます。そうすれば、部下もどんどん成長していきます。
優秀なリーダーなら、部下をこの「やる気のサイクル」で育成するのです。つまり、〈責任ある仕事→達成感→評価・承認→成長〉、このサイクルを回して、部下のモチべーションをあげ、部下育成に取り組むのです。
部下のやる気を育てる善循環システムを回そう!
3.部下とコミュニケーションをとるには
リーダーとして部下と向き合うときは、コミュニケーションが大きな部分を占めます。ある調査では、部下育成を行うとき、部下とのコミュニケーションに時間の60パーセントを使うべきだといっています。それほど「コミュニケーション」は部下育成において大事なことなのです。
コミュニケーションは、お互いの意思の疎通であり情報の共有です。リーダーは、部下の不満や悩みをきちんと把握し理解しているのか、自分の言ったことが正確に伝わっているのか、部下との関係が良好なのか、このような意思疎通や情報共有ができているのかについて、注意を払う必要があります。
部下とうまくコミュニケーションするには、リーダーは何をしたらよいのでしようか。次に具体策をいくつかあげてみます。
1. コミュニケーション・ギャップを埋める
ある雑誌に、「上下関係の亀裂」について、おもしろいアンケート記事が載っていました。役員など経営者層と、従業員との間に大きな意識のズレがあったことがわかったのです。
すなわち、経営者層の人たちは、「従業員との間で、人間関係が悪化したことは一度もない」または「一度くらいならある」と答えた人が、60パーセントでした。一方従業員へのアンケートでは、「上司との人間関係が何度も悪化したことがある」または「数回はある」と答えた人が70パーセントもあったのです。
リーダーは「一度言ったのでわかったはずだ」「コミュニケーションがうまくいっている」と思っても、部下はわかっていないことがあるものです。リーダーが部下に対して感じていることと、部下側がリーダーに対して思っていることには、大きなギャップがあるということです。
上司と部下のコミュニケーション・ギャップは、どうしても避けられないのが現実です。しかし、それを埋める努力は必要です。そのためには、上司と部下がお互いになすべきことがあります。
その一つ目は、期待すること・されることへの理解です。リーダーはまず、自分が会社から何を期待され、どんな成果をあげたらいいのか、についてきちんと理解します。そのうえで、その期待を達成するために、部下に何を求めるのかを部下に説明し、理解してもらいます。部下は「自分は会社からこんなことを期待されている」と、わかっていることが必要です。
リーダーは、ここを部下にきちんと理解させなければ、コミュニケーションは行き違ってしまいます。理解が得られれば、リーダーと部下はお互いに同じ目的を共有することができるのです。
次に、リーダーと部下双方が相手に望む姿を理解しているのか、という点です。リーダーから見て、「こういう部下であってほしい」ということを部下に理解させているか。また部下が、「リーダーたるもの、こうであってほしい」と思っていることをリーダーが理解しているのか。お互いにこれらを理解していることが大事です。
それを知ることによって、当然現状の姿とギャップが生じているのが発見できます。そのときは、お互いの課題を抽出して、解決に向けて歩み寄っていくことが必要になります。
2. 声を掛け合える雰囲気を作る
メールが発達している昨今、部下への伝達はメールでしているというリーダーがいました。彼は1日の大半を外に出て飛び回っていましたから、「メールは便利」と喜んでいたのです。次第に部下との会話が減っていきました。あるとき、メールで簡単な伝達事項を伝えた部下が、その解釈を誤って取引先を怒らせるというトラブルが発生しました。
このトラブルは、部下が悪かったのではなく、リーダーのメールが言葉足らずだったために起こったことでした。このとき、このリーダーは「部下と意思疎通がうまくいっていない」と痛感したのだそうです。
人間は、よく顔を合わせている人には自然と親しみがわきます。また声を掛け合っている人にも同様です。まず人間関係を良好に保ちたいのなら、気軽に声を掛け合う関係でなければなりません。リーダーは率先してこうした関係を築くことが大事です。
それには、朝晩のあいさつをし合ったり、顔を合わせるごとに声を掛け合ったりすることです。そうすれば、ちょっとした疑問があったときに聞きやすくなります。積み重ねた親しみがあれば、前述したような行き違いは起こらなかったはずです。
3. 言いたいことをうまく伝える
あるラグビーの監督が1人の選手に対して、いつも「おまえはパスが遅い」と言っていたそうです。その選手は、自分では早くパスしているつもりだったので、なぜそう言われるのかが理解できなかったそうです。その後、別の監督に代わったときに、新監督は「おまえはパスが2秒遅い」と、具体的な数字をあげて伝えました。そして、ビデオで良いパスと悪いパスの2つを並べて、スローモーションで見せたのだそうです。相手の手からボールが離れたところでビデオを止めて時間を計り、「良いパスはこれだ」。もう片方の悪いパスのビデオも同様に見せて、「おまえのパスは2秒遅れている」と説明したのです。
そのうえで、「お前は2秒だけ、このパスを早めたら必ずいい展開になる」とアドバイスしたのだそうです。その後、その選手はメキメキと腕をあげていったそうです。
部下は、リーダーの指導の仕方がうまいかどうかによって、とても変わります。指導の良し悪しは、コミュニケーションがうまいかどうかにかかっています。自分の言いたいことを、具体的に相手にわかる言葉で、さまざまな角度から理解できるように伝えることです。
4. 聞き上手になる
コミュニケーションをうまくするためのスキルには、聴くこと、話すこと、自己開示、言葉以外のもの (声の調子、しぐさ、態度など)の4つがあります。これらをいずれも磨いていくことが大事ですが、なかでも相手の話を聞くことは、非常に重要な要素です。
偉大なリーダーは、例外なく聞き上手として定評があります。その代表ともいえるのが、経営の神様といわれた松下幸之助氏です。彼の聞き上手は、誰からも賞賛されてきました。どんなに忙しくても、またどんな立場の相手でも、一生懸命に話を聞くのです。自分の知っている話ですら、初めて聞いたように「ほー、それはすごい」などとあいづちを入れながら聞くのです。また、誰にでも「あんた、どないに思う?」と聞くのが口グセだったといいます。聞き上手は、質問上手、質問力があるともいえるでしよう。彼は、こうして聞き知った情報を経営に生かしていたのです。
「聞く」ということは、単に聞いているのではなく、心を入れて注意深く、「聴く」ことです。聴くことによって、自分の知らなかった情報や知識が得られるばかりでなく、相手をよく理解できるようになります。するとコミュニケーションはうまくいき、相互理解が得られるようになっていきます。
聞き上手になると、相手から「あの人は話しやすい」と好感を持たれますし、相手も話を聞いてもらえることによって潜在的な能力が引き出され、やる気になってくるものです。
4.部下と上手に付き合うには
リーダーの本質が説かれているとして有名な書に孫子の「兵法」があります。この本は、今から2500年前の中国・春秋時代に、呉国の名将軍・孫武が著わした兵法のマニュアル書です。戦略論のバイブルとして、中国武将や日本の大名たちの必読書となり、諸葛孔明、武田信玄、徳川家康、そしてナポレオンなど、世界中の多くの名将の指針となりました。この本は戦術の書としてだけでなく、リーダーシップの本質が説かれているため、時代を超えて現代の経営者をはじめとするリーダーたちの指南書として、経営などに実践されています。
この本のなかに、理想的なリーダーシップの取り方の一つとして、次のような部分があります。
「卒を視ること嬰児の如し、故にこれと深谿に赴むくすべし。卒を視ること愛子の如し、故にこれと俱に死すべし。厚くして使うこと能わず、愛して令すること能わず、乱れて治むること能わざれば、譬えば驕子の若く、用うべからざるなり」
つまり、自分の兵士(部下)はかわいい赤ん坊のように扱うことだと説いています。「部下を赤ん坊のように可愛がれば、部下はそれに応えて深い渓谷のような危険なところにも一緒に行く。部下を自分の愛児のようにいつくしめば、部下は感激して一緒に死んでもくれるものだ。逆に厚遇し過ぎると生意気になって使いづらくなる。人を使うときは緩急自在にすることで、あまり愛に片寄ってもいけない」ということなのです。
部下とうまくつきあうのは難しいことですが、いくつかのポイントがあります。以下に述べてみます。
1. 信頼関係を築く
伏せたコップには、いくら水を注いでも水はたまりません。それと同様に、部下がリーダーに心を開いていないと、何をしても受け入れてもらえません。言っていることに対して、心のなかで「何だ、偉そうに言いやがって!」などと反発するようでは、聞く耳すら持っていないことになります。
こんな状態では、いくら指導や教育をしても受け入れてもらえません。まずは、部下としっかり信頼関係を築いておかなければなりません。
部下との信頼関係を築くには、日頃の言動が大事になります。思いつきでクルクル意見を変えず言動に一貫性を持つこと、言ったことは必ず実行すること、約束は必ず守ること、部下に心を開いて親密にしておくこと、部下のよきメンターになること――このようなことを心がけることです。そして、部下とうまくコミュニケーションをする、人間的な魅力を持つ、など、ここまで述べてきたようなリーダーの姿を実践しておくことが大事です。
2. 1人の部下でも本気でかかわる
リーダーは何人もの部下を相手にしなければなりませんが、それぞれの部下には真剣につきあうことが必要です。多忙ななかで何人もの部下に対応しなければならない――そんなときは、ていねいに対応することが面倒に思えるときがあるかもしれません。
しかし、これがよくないのです。リーダーにとってはたった1人の部下かもしれませんが、その部下の背後には最低でも10人の部下がいると思わなければなりません。
1対1でも真剣に話すと、本気でかかわることになります。すると、その部下は必ず同僚などに、そのとき話した内容や様子を伝えます。もしもリーダーに対して悪い感情を抱いている人がいても、話を間接的に聞くことによって、リーダーへの人間観が変わっていくこともあります。「案外いいやつだ」などと、誤解が解けることもあります。
ですから、リーダーにとってはたった1人の部下かもしれませんが、その後ろには多くの部下がいるということを心して、本気でかかわることが大事なのです。
3. 「良い人」ではなく「良き上司」になる
「良い人」というのは、優しいとか思いやりがあるということです。それらは、人間として当然あったほうがいいわけです。
では、良いリーダーというのは、どのような人をいうのでしょうか。リーダーは、たとえ優しさや思いやりがなくても、リーダーとしての役割をきちんとこなしていることが重要です。
目標達成のために組織を統率し、目指す方向に導くことができれば、大きな目的は達成できるわけです。そこには、「良い人」は求められません。しかし、「良き上司」は必ず必要となります。それは、部下が会社の理念や目標を理解し、それに沿った計画を実行してこそ、はじめて目標が達成できるからです。上司一人が奮闘しても会社の目標は達成できず、部下たちの力によらなければならないわけです。
「良き上司」は、部下を統率し、業績をあげさせることができる上司です。当たり前のようですが、「人の良さ」がいい上司だと勘違いしないことです。「良い人」を目指すのではなく、「良き上司」になれるようにすることです。
4. きちんとフォローを入れる
私がサラリーマン時代に、ある上司と会社ですごいけんかをしました。帰宅して妻と夕食をしていると、その上司から電話があったのです。その上司は、それまで家になど1回も電話をくれたことがありませんでした。怪訝な思いで電話に出ると、「ああ、オレや、昼間悪かったな、気にすんなよ」と、明るい声が受話器から飛び出してきました。あっけにとられているこちらをよそに、それだけ言うと「じゃあな」と電話を切ったのです。
受話器を置いたあと、こちらのモヤモヤしていた気持ちが救われたのを感じました。「案外、あれでも良いやつだな」と、そのとき思ったのです。たったそれだけのフォローでしたが、次の日からその上司に対する気持ちが変わった気がしました。
リーダーはとくに失敗や叱責のあとに、しっかりフォローを入れることは効果的です。
5.相手に考えさせる
リーダーは、部下に対して「こうしたほうがいい」「こうやったらうまくいくよ」と、ついつい口を出すことが多くなります。これは、ある意味で自分の考えや価値観を押し付けることになります。
しかし、できるだけ相手に考えさせて、やらせてみることが大事です。案外、自分が予期しないアイデアがあるかもしれませんし、自分と全く異なったやり方でうまくいくかもしれません。
ただ、部下に任せるときは、部下は失敗するかもしれません。危なっかしくて見ていられない感じがあるかもしれません。しかし、万一失敗しても、人間はそこから学ぶことが多くあります。
もちろん、リーダーとしてアドバイスをしたりヒントを与えたりすることは必要ですがあくまでも参考にしてもらうという態度にすることです。
6. 話を最後まで聞く
部下が一所懸命話しているのに、最後まで話を聞かず、途中でさえぎるリーダーがいます。これは、誰に対してもそうですが、リーダーはとくに気に入らない部下の話をさえぎりがちです。「だからさー」「いやそうじゃなくってー」などと、最初から頭ごなしの能度の人がいるのは困ったものです。
話の途中で口をはさまれると、部下は口をつぐんでしまいます。すると結局、部下が何を考えているのかがわからなくなり、すれ違ってしまう原因になります。
最初の言葉だけでは、その先の話の方向は見通すことができません。部下の話は、しっかり最後まできちんと聞くことです。
そうすれば、部下は次のときも話がしやすくなりますし、この積み重ねがお互いの信頼関係を築くことになります。こうした関係のなかから、部下は上司に対する報告のしかたも上達してくるものです。
7. オープンマインドで接する
「心はパラシュート」という言葉があります。これは、心もパラシュートも、開かなければ使えないということです。リーダーは、部下に心を開いて接する心がけを持たなければなりません。コミュニケーションしても、何か引っかかるものを感じさせるような態度では、部下は疑心暗鬼な気持ちを抱いてしまい、身を入れて仕事をすることができません。
自分はその部下をどう見ているのか、その部下に何を期待しているのか、今どのような方向を目指しているのか、なぜこの計画が必要なのか、仕事に対していかなる気持ちで取り組んでいるか。このようなことを折りにふれて率直に心を開いて話すことです。
会議の場で、指示命令の折に、あるいは移動の車の中や食事の席でもかまいません。リーダーが率直に話せば、部下はリーダーの苦しみや大変さを理解するようになります。
リーダーが部下に心を開いてこそ、部下も心を開きます。自分のことをオープンに表現している上司は、部下から見ても魅力を感じるものです。そうしたところから、「よし、自分も一緒に戦おう」という気概も生まれてくるのです。
8. ノミニケーションは、ほどほどに
「ノミニケーション (部下と酒を一緒に飲むこと)がコミュニケーションの近道だ」と言う人がいます。たしかに、酒の場は心を開きやすく、意思疎通がはかりやすいというメリットがあります。
しかし、あまり頻繁にやりすぎると、不公平感を持つ人が出たり、誤解を招きがちです。「あいつはよく連れて行ってもらっているのに、オレは全く誘ってくれない」などとひがむ人が出てくることがあります。 あるいは、「あいつを連れて行って秘密の話でもしたのではないか」などと勘ぐられることにもなりかねません。
最近の若い人のなかには、上司との酒席のつきあいを好まない人も多くいます。アフター5のつきあいは、ほどほどにすることです。もし、コミュニケーションをとりたいのなら、酒が入らない場できちんととるのが原則です。
9. よくほめる、よく叱る
仕事では、どうしてもほめることより叱ることのほうが多くなりがちです。しかし、リーダーにとっては、「部下をほめる」ということが重要なポイントとなります。ほめられた部下は自分のやったことが認められたことで喜びを感じますし、モチべーションが高まるという効果があります。
ほめるときには「よかったね」と言うだけでなく、どこがどう良かったのかを具体的にほめるのが上手なほめ方です。「キミの報告のしかたは、要点を先に言ってくれるので、とてもわかりやすい」「キミの忍耐力はすばらしい。そのおかげで完成したようなものだ」などと、その人ならではの長所をほめるのです。このように、長所をよく見てほめようと意識すると、ほめる場面が多くなっていきます。
ほめることと同じぐらいに大事なのは、部下をしっかり叱ることです。ほめること・叱ることのどちらかに片寄っていると問題ですから、バランスを取ることが大事です。
織田信長はリーダーとして傑出した才能を持ち、信賞必罰 (功績に対して必ず賞し罪は必ず罰する)が非常に的確でした。ほめること・叱ることをうまく取り入れて、強いリーダーシップを発揮し、部下を統率しました。しかし、明智光秀にだけは、叱り方が激しくしつこ過ぎてしまったのです。それが恨みを買って結局本能寺の変につながり、自分の命を落とすことになってしまいました。
叱るのは恨みにつながることがありますから、難しいものです。叱るときは自分の価値判断を加えず、「おまえはいつも」などと私慣を加えて非難がましく言わないことです。
ほめるとき、叱るときは、どの行動が賞賛に価するのか(または、問題があったのか)、取った行動の具体的事実にフォーカスして、きちんと伝えることです。
次に、それに対して自分がどのように感じたのか、率直に伝えます。「あなたは、クレームに対してただちに対応してくれたから、お客様が喜んでお礼の電話をよこした。オレはすごく婿しかった。今度の社内報に掲載しようと思っている」などと、率直に表現するのです。
具体的にどの行動に対してほめている (または、叱っている)のか、どのような影響があったのか、自分がどんな感情を持ったのか。これら3つの要素を網羅すると、ほめるときも叱るときも部下は納得できるものです。
10. マネージメント・ポリシーを明確にする
リーダーは、部下のマネージャーとして、自分のポリシーを明確にしておく必要があります。それによって、部下は、「この仕事は、このポリシーのこの部分に基づいてこういうふうになったのだ」とか、「このポリシーから考えたので、こういう行動や態度をオレたちに取ったのだな」と、理解できます。
これによって、部下とのコミュニケーションや理解が深まります。
たとえば、私が以前作ったマネージメント・ポリシーは、「部下への最大の貢献は目標達成をさせてあげること」というものでした。ですから、「私が部下を怒ったり叱ったりしても、すべて部下に目標達成をさせてあげるための手段なのだ」と話をして、部下に納得してもらいました。
そして、これを実行していくにあたって、伝えた8項目がありました。
① 自由と規律のバランスを保つ、
②自ら動こうとする環境に配慮する、
③実力主義で、やったらやっただけ報いていく、
④コミュニケーションを大切にしていく、
⑤お互いに説明責任と結果責任を持とう、
⑥どんどん権限委譲して、自分にしかできない仕事にフォー カスする、
⑦徹底した行動の質と量を追究していく、
⑧目的、目標を明確にして仕事をする。
これら8項目がマネージメント・ポリシーだと、部下に伝えるとともに、「この8項目に照らして、上司である私の言動に疑問や反論があったら、遠慮なく言ってほしい」と明言しました。これによって、コミュニケーションが大変にうまくいったのです。
5.部下に「愛」は注いでも、「情」は注がない
リーダーは、部下に対して言うべきことをきちんと言わなければなりません。とくにミスをしたり失敗を繰り返したりするときは、きちんと言うべきことを言わなければなりません。
このとき、「愛」は注ぐ必要がありますが、「情」は決してからめないことです。「言ったらかわいそうだ」とか「これを言ったら、傷ついてやる気をなくすのではないか」と考えるときがあるかもしれません。しかし、部下に愛情を持っているのであれば、そうした情に流されず、告げるべきときには告げなければならないはずです。
言ったことによって、お互いがいっときは嫌な思いをしても、長い目で見ればその人も成長できるはずです。また、その部下を信頼し、今後も一緒にやっていきたいと思うのであれば、気持ちは部下にも伝わるものです。
「愛」を持って部下を育てる、と思うときは、その人にはどういう状態が一番大切なのかを考えてみます。その人のやり甲斐や生き甲斐、喜び、得意、好き、幸せ感などといったもののなかで、何を最も大事にしているのか、ということです。
たとえば、「あの部下は本当にこの会社で仕事をすることが幸せなのか」「得意な能力を発揮できるのか」と考えてみます。その結果、この会社に置いておくことは、その部下にとって不幸なのではないか、と考えられる場合があります。
そのときは、その人がいくら「この仕事を続けたい」と言っても、情に流されず、部門を移すとか、ほかの仕事を用意することも生じてきます。ときには、会社のエゴで特別に優秀な社員を飼い殺しにしているという状態もあります。そんな場合には、転職をうながす必要があるかもしれません。
本当に愛があるのなら、どう考えてもその人のためにならないと思われるケースでは、きちんとそのことを告げることが必要なのです。
愛を注ぐけれど情も注いでしまう人は、しょせん改革者にはなれません。リーダーであるならば、愛をもって情を切って行動する、そのあたりの感情をしっかり使い分ける冷静さを持たなければなりません。
この無料レポートが、リーダーであるあなたの一歩踏み出すキッカケになったのなら嬉しいです。
もし、「さらに学んでみたいなと思った方」は、
全4回コースの無料オンライン講座をご用意していますので、
ご活用ください!!